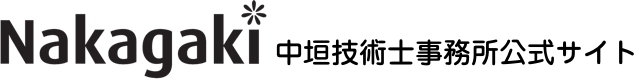
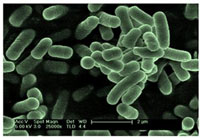 プロバイオティクスは”適切な量を摂取するとヒトに健康上の利益をもたらす生きた微生物”と定義されています。FAO/WHOによれば、従来はヒトの消化管から分離された微生物のみが、プロバオティクスとしての使用を推奨されていました。
プロバイオティクスは”適切な量を摂取するとヒトに健康上の利益をもたらす生きた微生物”と定義されています。FAO/WHOによれば、従来はヒトの消化管から分離された微生物のみが、プロバオティクスとしての使用を推奨されていました。
経口摂取された微生物は胆汁などのヒトの防御システムに遭遇します。胆汁および胆汁酸に耐える微生物の能力が消化管内での生存にとって重要です。胆汁酸塩加水分解酵素活性による胆汁酸代謝は、プロバイオティクス株を選択するための重要なEFSA基準です(EFSA:欧州食品安全機関)。新たな証拠により様々な発酵食品に関連する微生物のプロバイオティクスとしての可能性が強調されるようになり、起源に関係なく胆汁酸塩を加水分解する能力が、プロバイオティクスの選択基準に含まれるようになりました。”ノンディリーPLANTA”に含まれている植物性発酵食品由来のプランタルム菌株(Lactobacillus plantarum ECGC13110402)は、高い胆汁酸加水分解酵素活性を持つプロバイオティクス乳酸菌です。
ノンデイリー PLANTA
コーカサスのケフィア
フィンランドのヴィーリ
ブルガリアのヨーグルト
ポリフェノールたっぷり、オーガニック
カナダの森の大自然からのピュアな贈り物
雅蜂園の国産はちみつ
コント・ド・プロヴァンスのジャム
ケフィア菌に、ビフィズス菌をプラス
ひざ関節の違和感の軽減をサポート
 私達は自社のオリジナル商品について、商品価値を高めるべく乳酸菌・発酵乳の健康効果について研究を進めていますが、最近この分野に世界の科学者の関心が高まり、沢山の研究論文が発表されるようになりました。私は自社の研究成果の紹介ばかりでなく、世界中で発表される先端的研究論文を紹介して、皆様と知識を共有することによって、私達の商品に対する理解も深めていただけるのではないかと考えて、乳酸菌、プロバイオティクス、腸内細菌叢の働きが、"ここまでわかった"、”ここまでしかわかっていない”と言うことをお伝えしていきたいと思います。
私達は自社のオリジナル商品について、商品価値を高めるべく乳酸菌・発酵乳の健康効果について研究を進めていますが、最近この分野に世界の科学者の関心が高まり、沢山の研究論文が発表されるようになりました。私は自社の研究成果の紹介ばかりでなく、世界中で発表される先端的研究論文を紹介して、皆様と知識を共有することによって、私達の商品に対する理解も深めていただけるのではないかと考えて、乳酸菌、プロバイオティクス、腸内細菌叢の働きが、"ここまでわかった"、”ここまでしかわかっていない”と言うことをお伝えしていきたいと思います。
なお、弊社はブルガリアから有機アロニア果汁を輸入していますが、ポリフェノール含有量の高いアロニア果汁の生理活性成分が世界の科学者の注目を集め、多くの研究論文が発表されていますので、最新の研究論文を紹介したいと思います。
タイトル:"栄養摂取によるサルコペニア対策:アロニア・メラノカルパの抗炎症・抗酸化作用"
加齢に伴う骨格筋量、筋力、機能の進行性低下であるサルコペニアは、高齢者の罹患率、虚弱性、そして生活の質の低下の大きな要因です。サルコペニアは、酸化ストレスと慢性炎症が中心的な役割を果たす、複雑かつ多因子性の病態です。アロニア・メラノカルパ(ブラックチョークベリー)は、強力な抗酸化作用と抗炎症作用を持つアントシアニンとプロアントシアニジンを豊富に含むポリフェノール豊富な果物として注目されています。前臨床、臨床、栄養学的研究によると、アロニア・メラノカルパの生理活性物質は、酸化還元バランスを調節し、炎症性サイトカインの産生を抑制し、抗酸化酵素の活性を高め、骨格筋の健康に重要な代謝および再生シグナル伝達経路を調節することが示されています。著者らによるとこのレビューの目的は、サルコペニアにおける酸化ストレスと炎症の分子的・細胞的相互作用に関する最新の研究を要約し、アロニア・メラノカルパの栄養介入としての可能性を評価することです。全体として、データは、アロニア・メラノカルパがサルコペニアの予防と治療のための機能性食品および栄養補助食品の候補となる可能性を示唆していると述べています。(詳しくはタイトルをクリックして日本語に訳した論文を読んでください)。
1)目次をつけています。長文の論文をすべて読み通すのは疲れますから、目次から興味のある項目を選んで、クリックすれはその項目を読めるようにしています。
2)原論文では繰り返し出てくる用語は略語で表記していますが、翻訳文ではどこから読んでもわかりやすいよいうに、略語の表記を廃しすべて元の用語で表記しています。但し、略語が巷間に慣用されているか、あるいは今後慣用されると思われる用語は略語のまま記載しています。
3)重要な用語はカッコ内の訳者注によって簡単な説明をしています。
4) 菌名は正確を期するために英語表記にしていますが、初めて読む方にもわかりやすくするために、論文の内容によってはカタカナ表記に変更しています。原則としてオリジナル論文は英語表記に、レビューはカタカナ表記にしています。
これまで紹介してきた自社の研究論文は"研究発表"に、世界の研究論文は"文献調査"に、それぞれ収録しています。